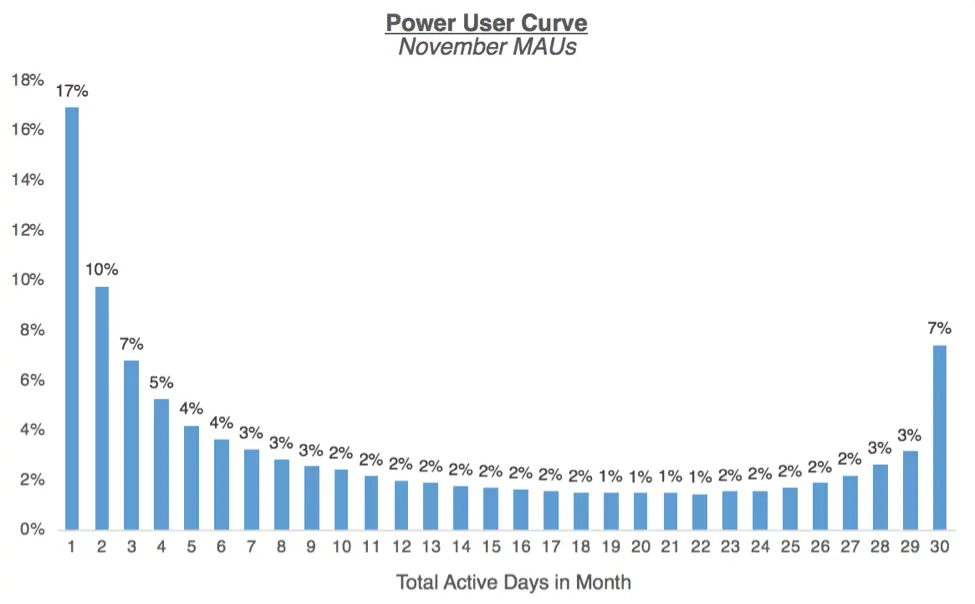二つ名とは、本名以外の正式名称ではない呼び名のことである。「別名」や「あだ名」を含む場合もあるが、その対象の特徴や性質、印象を端的に表現した言い回しを「あだ名」「通り名」などと区別して「二つ名」と呼ぶことが多い。読みは「ふたつな」。
個性的な戦国武将、著名人、スポーツ選手(チーム)、政治家などに対して、尊敬や畏怖、崇拝の念を込めて付けられることが多い。「甲斐の虎」「東洋の魔女」「平成の怪物」「浪速のジョー」といった著名な表現例がある。
近年、お笑いのテレビバラエティー番組でお笑い芸人に付けられる異名キャッチコピーなども「二つ名」に該当する。